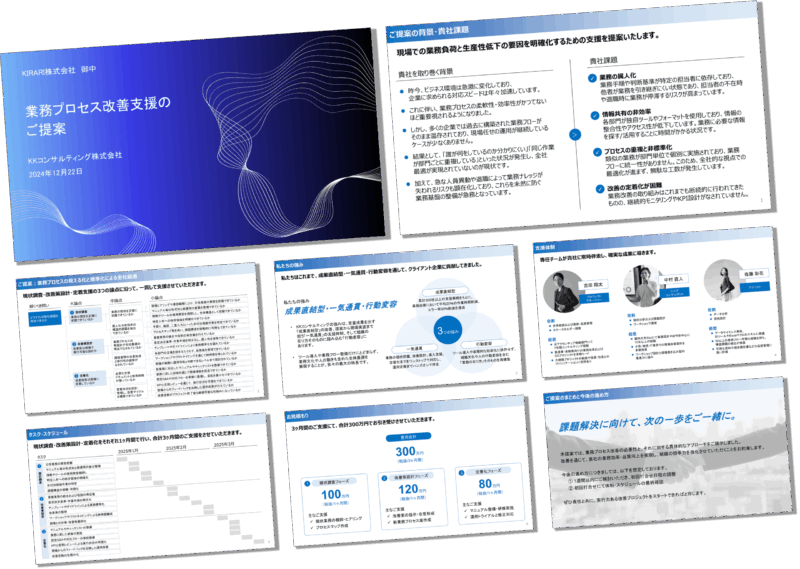ビジネスの現場では、良いアイデアや優れたサービスがあっても、それを正しく伝えられなければ成果につながりません。提案資料/提案書は、単なる情報のまとめではなく、相手の理解と納得を得て行動へ導くための強力な武器です。
しかし、いざ作成となると「どんな構成にすればいいのか」「どこまで情報を入れるべきか」「デザインはどう整えればいいのか」と悩む人も多いはずです。
本記事では、提案資料/提案書の基本構成からストーリー設計、デザインの工夫、よくある失敗例と改善策までを徹底解説します。資料のテンプレートも用意しているので、明日からの提案資料/提案書作りにすぐ活かすことができ、成約率を高める一歩を踏み出せるでしょう。
なお、資料作成にお困りの方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください。1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます!

.png)
本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)
創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。
外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案や資料作成に関する豊富な経験を有する。
はじめに:無料テンプレートのご紹介
最初に、無料の提案資料/提案書テンプレートを掲載させていただきます。
無料の提案資料/提案書テンプレートは時間短縮に有効ですが、そのまま使うと他社と似たような資料になりやすいというリスクがあります。ブランドカラーやロゴを反映させ、独自性を確保しましょう。また、テンプレートはあくまで「型」であり、中身のストーリーが弱ければ説得力は生まれません。状況に合わせてカスタマイズし、自社やクライアントに最適化することが必要です。
こうした点に注意しながら、ぜひ上手く活用してみてください!
提案資料/提案書とは?役割と重要性
提案資料/提案書とは何かを考えるとき、多くの人は単に「会社案内の延長」や「パワーポイントで作る説明用のスライド」といったイメージを思い浮かべるかもしれません。しかし、提案資料/提案書はもっと深い意味を持っています。
単に情報を列挙するだけでなく、相手の意思決定を後押しするための大切なツールであり、読む人の心理を動かし、行動を起こさせるための設計が必要です。優れた提案資料/提案書は、現状の課題を論理的に示し、その解決策を魅力的かつ納得感のある形で提示し、さらに次に取るべきアクションまで明確に示します。これにより、商談や社内稟議のスピードが加速し、意思決定が前に進みます。
逆に、構成が整理されていない資料、論理の飛躍がある資料、結論が最後まで示されない資料は、相手に余計なストレスを与え、判断を先送りにさせる原因となります。「資料を作ったのに反応が鈍い」「なぜか通らない」といった問題の多くは、資料の構成や情報の出し方に起因しています。提案資料/提案書は単なる紙の束でもスライドファイルでもなく、プレゼンテーションや営業活動、社内稟議を成功に導くための「戦略ツール」です。
近年では、提案資料/提案書が使われる場面はさらに多様化しています。対面営業だけでなく、オンライン商談、事前共有のメール添付、社内回覧など、資料だけが相手の判断材料となるケースが増えています。特にオンラインでは、提案者の声や表情、身振りといった非言語情報が伝わりにくいため、資料そのものが「説得力」を持たなければなりません。資料が整っていればいるほど、提案者が同席していない場面でも社内で検討が進みやすくなり、結果的に成約率も高まります。

提案資料/提案書の基本構成とストーリー設計
提案資料/提案書を構成する上では、まず冒頭で「この資料は何のためのものか」を明確に示すことが必要です。表紙には提案名、クライアント名、日付、自社名を入れ、見ただけで資料の趣旨が分かるようにします。導入部分では、提案の背景や目的を端的に説明し、読み手の頭の中に「なるほど、これは重要な提案なのだ」という問題意識を芽生えさせます。そのうえで、次にご説明するような「現状分析」「課題とニーズの明確化」「解決策の提示」「期待効果と次のアクションの明示」に取り組んでいく必要があります。
現状分析
ここでは市場環境や業界トレンド、競合状況、クライアントが置かれている現状を、客観的なデータを用いて整理します。グラフや統計を用いれば説得力が増し、「私たちは御社の状況を理解しています」というメッセージを伝えられます。ただし、単にデータを並べるのではなく、そのデータから読み取れる意味を解釈して言語化することが大切です。現状認識と課題認識がずれると、その後の提案全体がかみ合わなくなり、せっかくの提案が響かなくなります。

課題とニーズの明確化
現状分析が終わったら、次は課題とニーズを具体的に提示します。多くの提案資料/提案書が陥る失敗は、現状分析と課題提示が分離しており、「結局どこが問題なのか」が曖昧になっているケースです。
課題は、現状分析の流れから論理的に導き出される必要があります。「売上が低迷している」という表現では曖昧すぎるため、「主要チャネルでの新規顧客獲得コストが過去1年で30%増加し、利益率を圧迫している」というように、数字を交えて具体的に示すことが重要です。こうすることで、相手は「確かに手を打たなければならない」と納得します。
さらに、課題を提示する際には、課題の優先順位も示すと良いでしょう。すべての課題に同時に手をつけることは現実的ではありません。優先度の高い課題から解決していくことが提案の現実性を高めます。

解決策の提示
課題が明確になったら、その解決策を提示します。ここで重要なのは、課題と解決策が一対一で対応していることが一目でわかる構成にすることです。「この課題にはこの施策」「この問題にはこの対応」というように対応関係を明確にすると、論理の飛躍がなくなります。
また解決策は、抽象的なスローガンではなく、具体的な行動計画や導入ステップまで落とし込むことが大切です。スケジュール、必要なリソース、役割分担、予想されるリスクとその対策まで明示すると、相手は「現実的に実行できそうだ」と感じます。
複数の選択肢がある場合は、メリットとデメリットを比較表で示すと、意思決定がスムーズになります。また、施策を実施した場合のシミュレーションや、過去の成功事例を紹介することも効果的です。

期待効果と次のアクションの明示
提案資料/提案書の最後には、期待効果と次のアクションを必ず明示します。提案を実行した場合にどのような成果が得られるのか、可能な限り定量的に示しましょう。たとえば「導入から6か月で新規顧客獲得コストが20%削減される見込みです」「営業効率が1.5倍に向上します」など、具体的な数字があると説得力が増します。
さらに、相手に次に取ってほしい行動を明示することが重要です。「この内容でご検討いただき、来週末までにご回答ください」「次回は詳細設計フェーズの打ち合わせをお願いします」といった形で、期限やアクションを明確にすると、提案が実際の行動につながりやすくなります。

情報量はできる限り削減せよ
提案資料/提案書を作る際には、どれだけ情報を盛り込むかの判断が極めて重要です。多くの人は「情報量が多いほど説得力が増す」と考えがちですが、実際には逆効果になることが少なくありません。30枚、40枚と長大な資料になればなるほど、読み手は途中で集中力を失い、肝心な結論や行動喚起までたどり着かない可能性が高まります。必要なのは、情報を削ぎ落とし、読む人が迷わず理解できる構成にする勇気です。
情報は少なすぎても多すぎてもいけません。少なすぎれば説得力がなく、質問攻めにあうリスクが高まりますし、多すぎれば本当に重要なメッセージが埋もれてしまいます。理想は、読み手が3分、5分といった限られた時間であっても要点を把握できる構成です。1スライドごとに「何を伝えるためのページか」を明確にし、作成時には必ず「このスライドは本当に必要か」「なくしても話の流れは成立するか」と自問自答することで、余計なスライドを減らすことができます。
また、長さだけでなく情報の密度も調整する必要があります。1枚に要素を詰め込みすぎると、文字が小さくなり、視覚的な負担が増えます。複雑な情報は複数のスライドに分けて段階的に提示した方が、相手の理解度は高まります。たとえば、現状分析→課題整理→解決策提示を一枚に押し込むのではなく、それぞれを1〜2枚ずつ丁寧に分けることで、ストーリーの流れがスムーズになります。
さらに、相手の立場や資料を使う場面も考慮しましょう。経営層向けなら要点を絞った短めの資料、現場メンバー向けなら詳細情報を多めに含めた資料など、読み手に合わせた情報量の最適化が重要です。この調整を怠ると、せっかくの提案が「長いだけ」「薄いだけ」と評価されかねません。

デザインの成否が「読みたい」「読みたくない」を左右する
提案資料/提案書のデザインは、単なる装飾ではなく情報の伝達効率を最大化するための重要な仕掛けです。どれほど論理的に優れた内容であっても、見づらい資料や雑然としたスライドは読む気を削ぎ、相手にストレスを与えます。逆に、整理されたデザインと適切なビジュアルを用いることで、複雑な情報も直感的に理解でき、提案全体の説得力が飛躍的に高まります。
フォントは、ビジネスシーンでは可読性の高いMSPゴシックやMeiryo UIを選ぶのが一般的です。見出しには太字、本文には標準ウェイトを使うことで視覚的な階層構造をめいじできます。文字サイズは、プロジェクター投影なら20ポイント以上、紙やPDF配布用なら14ポイント以上を目安にすると読みやすくなります。行間は1.3〜1.5倍程度が理想で、詰めすぎると圧迫感が出て、開けすぎると間延びした印象になります。
配色はブランドカラーを基調にしつつ、補助色は2〜3色に抑えると全体に統一感が出ます。背景と文字のコントラストは十分に確保し、可読性を優先しましょう。色が持つ心理的効果(青は信頼感や誠実さ、赤は注意や行動喚起、緑は安心感や成長 など)も念頭に置いておくと、より一層プロフェッショナルな提案資料/提案書が出来上がります。
余白は「無駄なスペース」ではなく、情報を整理するためのフレームとして機能します。適切なマージンを確保することで、要素が際立ち、視線誘導がスムーズになります。詰め込みすぎると情報の優先度が見えづらくなるため、思い切って余白を広めに取ると高級感が生まれ、読み手の心理的負荷も軽減されます。
グラフや図解は、文章よりも速く情報を伝えられる強力なツールです。ただし、細かい数字や凡例が多すぎると逆に分かりづらくなります。棒グラフや円グラフは用途に応じて使い分け、比較や変化を強調する際は色や注釈を工夫します。アイコンや写真も効果的に使えば視覚的なアクセントとなり、記憶に残りやすくなりますが、多用すると散漫な印象になるため注意が必要です。
最も重要なのは、デザインの一貫性です。フォントの種類、サイズ、見出しの位置、色使いがスライドごとに違っていると、資料全体がちぐはぐに見えてしまいます。最後に全ページを並べて俯瞰し、トーンやスタイルが統一されているかを確認することが仕上げのステップとして有効です。

提案資料/提案書の作成プロセス
提案資料/提案書作成は、単なるスライド作成ではなく、提案そのものの設計と言うこともできます。
最初にやるべきは、提案のゴールを明確にすることです。「契約を結びたい」「次の検討ステップに進めたい」「予算承認を得たい」など、ゴールによって資料の構成も重点も変わります。ゴールが曖昧なまま資料を作り始めると、情報が散漫になり、結局何を伝えたかったのかが不明瞭な資料になりがちです。
次に、情報収集と分析を行います。市場データ、顧客の声、競合の動向、社内の実績など、多角的に素材を集めます。集めた情報を整理し、課題と解決策を論理的に紐付けることで、資料の土台となるストーリーが浮かび上がります。ただし、情報収集が膨大になっても時間だけを消費するだけなので、提案のゴール達成に必要な情報のみに限定して集めるようにしましょう。
骨子(アウトライン)作成は最重要ステップの一つです。1枚ごとのメッセージ、ページ順序、全体の流れを先に設計することで、無駄な手戻りを減らせます。骨子段階で社内レビューを行えば、方向性が早期に共有され、後工程での大幅修正が不要になります。いきなり各スライドを作り込み始めることが、最も手戻りが発生する愚かな行為です。
スライド化のフェーズでは、文章を端的にまとめ、図解やグラフを用いて視覚的に理解しやすい形にします。初稿ができたら、第三者によるレビューを受けると、自分では気づかない論理の飛躍や表現の曖昧さが明確になります。レビュー後の修正を経て、最終版が完成します。
最後のステップとして、プレゼンテーションのリハーサルを行い、実際の話し方や時間配分を確認します。リハーサルで引っかかった箇所は、資料やスクリプトを再調整して改善します。想定質問に対する答えを準備しておくと、本番で自信を持って説明できます。

よくある失敗と改善のポイント
提案資料/提案書でよく見られる失敗も簡単にご紹介しておきましょう。
まずよく見られるのが、情報量が多すぎて相手が途中で飽きてしまうケースです。改善するには、要点を3〜5個に絞り、重要なメッセージを繰り返し強調することが重要です。
次に、結論が最後まで出てこない資料も失敗例の一つです。人は冒頭で結論を知りたい生き物です。最初に「結論→根拠→詳細説明」の順で見せることで、相手は安心して内容を追えます。
デザインの不統一も信頼性を下げる要因です。フォントや色、見出し位置を統一するだけで、資料全体が引き締まり、プロフェッショナルな印象を与えます。
さらに、相手視点が欠けた資料は、自社の自己満足で終わりがちです。常に「このページは相手にどんな価値を与えるか」を意識し、相手のメリットや課題解決に焦点を当てて作成しましょう。
最後に、次のアクションが明示されていない資料は、相手を行動に移させるチャンスを逃します。締切日や具体的な依頼内容を明確に記載し、相手が迷わず行動できるように導くことが成功の鍵です。
こうした失敗ポイントは代表的なものですが、提案資料/提案書作成中、あるいは作成後にチェックしていただければ、より一層素晴らしい提案資料/提案書が完成するでしょう。

まとめ
提案資料/提案書は、提案者の思考を可視化し、相手を納得させ行動に移させるためのツールです。情報を取捨選択し、ストーリーを練り、デザインを整えることで、単なる資料から相手を動かす武器へと昇華します。作成の手間はコストではなく、成功率を高めるための投資です。自社視点ではなく相手視点に立ち、課題解決のシナリオを描き、論理と感情の両面から説得力を持たせることで、提案資料/提案書はあなたのビジネスを加速させる強力なパートナーとなるでしょう。
ちなみに、「自分で資料を作るのは大変・・・」「プロの力を借りたい!」という方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください!1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。

目次