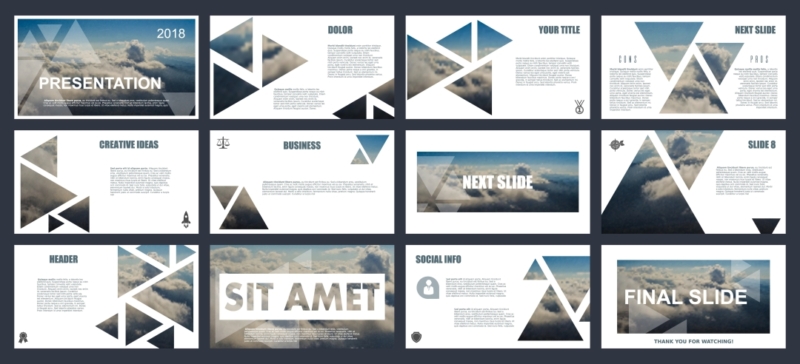会社紹介資料は、営業や採用の成果に直結する重要な資料です。しかし、多くの企業では情報を詰め込みすぎたり、誰にでも同じ内容を見せてしまったりすることで、効果を十分に発揮できていません。
本コラムでは、会社紹介資料の役割や営業・採用それぞれの目的の違いを解説し、成果を高めるために必要な共通ポイントを整理します。その上で、実務にすぐ活かせる10の作成ポイントを具体的に紹介します。
ターゲットの明確化、ストーリー構成、デザインの工夫、数字の示し方、CTA設計、定期的な更新方法までを体系的に解説することで、読み終えた後に自社の資料を改善できる実践的な指針を得られるはずです!
なお、資料作成にお困りの方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください。1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます!

.png)
本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)
創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。
外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案や資料作成に関する豊富な経験を有する。
会社紹介資料の役割とは
会社紹介資料は単なる会社案内やパンフレットではありません。それは企業の第一印象を形づくり、相手の理解と行動を促す戦略的な資料です。
営業の場面では、顧客が抱える課題を自社の製品やサービスでどう解決できるのかを明確に伝えることで商談の成否を左右します。採用の場面では、応募者が企業文化やビジョンに共感し、安心感を得て応募行動へとつながるよう導く役割を担います。
重要なのは、会社紹介資料が「相手視点での意思決定」を支援するという点です。顧客は競合他社と比較検討し、限られた時間で導入可否を判断します。応募者も複数社を並べ、条件だけでなく社風や将来性を短時間で見極めます。その際、情報が雑然と並んでいる資料では相手の理解が進まず、選ばれる可能性を下げてしまいます。
会社紹介資料の価値は、単に情報を並べることではなく、相手の理解を助け、信頼を高め、行動へとつなげることにあります。営業や採用はもちろん、投資・パートナー提携・社内共有と多方面で機能するからこそ、その設計には一貫した戦略が必要になります。

営業と採用で異なる資料の目的
営業と採用では、会社紹介資料に求められる役割が大きく異なります。
営業資料の目的は、顧客課題を理解し、自社が提供する解決策を最適な選択肢として提示することです。営業現場では、課題の提示、解決アプローチ、自社の優位性、導入実績、ROI、価格やスケジュール、CTA(Call To Action:行動喚起)という流れが典型的です。論理性が重要であり、数値データや実績を根拠にした説明が欠かせません。例えば「導入後のコスト削減率20%」「業務効率化30%改善」といった具体的な成果は、顧客の意思決定を強く後押しします。
一方で採用資料の目的は、応募者が安心し共感して応募意欲を高めることです。給与や福利厚生の条件提示は当然必要ですが、それ以上に企業理念、社員の働き方、キャリア形成の可能性、職場の雰囲気といった情報が応募者にとって重要です。新卒には研修制度や若手社員の声が響き、中途採用ではスキル活用やキャリアパスの具体性が求められます。
営業は論理で信頼を獲得し、採用は感情に働きかけて意欲を引き出す。この違いを認識せず同じ資料を両方に流用すると、誰にも刺さらない結果になります。それぞれに目的を定義し、伝える内容やトーンを設計することが成果に直結するわけです。
それでは、会社紹介資料の具体的な作成ポイントを見ていきましょう!

ポイント1:ターゲットを明確にする
ターゲットの設定は会社紹介資料作成の出発点です。営業資料では顧客の業種、規模、課題感、予算規模、意思決定プロセスによって必要な情報が変わります。大企業には安定性と過去実績、中小企業にはコスト削減や即効性といった要素を強調するのが有効です。
採用資料でも、新卒と中途で重視される情報は違います。新卒は研修制度や先輩社員の声、中途はキャリアパスや評価制度、裁量権が重視されます。
ターゲットが曖昧な資料は情報過多になり、誰にも刺さらないものになります。実際にあるIT企業では、営業・採用・投資家向けを1つの資料にまとめていたため、どの相手にも適切に届かず成果が上がりませんでした。しかし、ターゲットごとに資料を分けて最適化したところ、営業成約率は15%向上し、採用エントリーは20%以上増加しました。
誰に向けて資料を作るのかを最初に明確化することが、すべての出発点です。

ポイント2:ストーリー性を持たせる
会社紹介資料を単なる情報の羅列にしてしまうと印象に残りません。人は物語で理解すると記憶に残りやすいため、ストーリー性を持たせることが重要です。
営業資料なら、顧客課題の提示→解決策の提案→導入実績→成果という物語にするのが効果的です。顧客は自社に置き換えてイメージしやすくなります。
採用資料では、企業の成長物語や社員のキャリアの歩みをストーリーで示すと応募者の共感を得やすくなります。
あるメーカーは従来、沿革や数字を羅列した採用資料を使っていましたが、社員の1日を紹介するページを加えたところ学生の反応が一変しました。「入社後の姿が想像できた」という声が増え、エントリー数は前年比30%以上伸びました。
ストーリー性は相手の感情に訴え、行動へ導く力を持ちます。

ポイント3:1スライド1メッセージを徹底する
1ページに複数のメッセージを詰め込むと相手は混乱します。資料は1スライド1メッセージを徹底するべきです。
営業資料なら、サービス特徴、価格、導入事例、効果を分けて1枚ずつ配置します。採用資料でも理念、社風、制度、社員の声を分割する方が応募者にとって理解しやすくなります。
あるSaaS企業は以前、情報を1ページにまとめすぎていましたが、1ページ1メッセージの原則を守るように改めたところ、商談時間が短縮し、質問が本質的なものに集中するようになりました。
余白を活用し、見た瞬間に伝えたいことが分かるように整理することが成果に直結します。

ポイント4:視覚的に理解できるデザインにする
文章ばかりの資料は相手に負担を与えます。だからこそ、デザインの工夫で「見た瞬間に意味がわかる」資料にすることが大切です。
営業資料では、成果や実績をグラフやチャートで示すと直感的に理解されやすくなります。あるIT系企業は導入効果を棒グラフで示し、導入前と導入後の業務時間を比較しました。その結果、文字説明だけの頃よりも顧客の理解が早く、商談の質も高まったと報告されています。
採用資料では、社員やオフィスの写真を活用することが有効です。ある人材サービス企業は、働く社員の姿や社内の雰囲気を写真で示すことで応募者の安心感を高め、エントリー数の増加につなげました。
また、配色やフォント、余白の使い方も重要です。あるメーカーは余白を大胆に使い、情報を絞り込むことで可読性と洗練された印象を両立させています。詰め込みすぎよりも、情報を削ぎ落とす勇気が資料の完成度を高めます。

ポイント5:数字や実績を具体的に示す
抽象的な表現だけでは説得力が足りません。数字や実績を提示することで、相手に安心感を与え、判断を後押しできます。
営業資料では「コスト削減率20%」「生産性30%向上」など具体的な数値を示すと効果的です。あるBtoBサービス企業は、導入後の効果を数値化して掲載した結果、顧客から「投資判断がしやすい」と評価され、成約率が高まりました。
採用資料では、定着率やキャリアアップ率などを数値で見せると信頼につながります。ある新卒採用企業は「3年後の定着率」や「若手管理職の比率」を明示することで、応募者に安心感を与え、エントリー数の増加を実現しました。
数値は単なるデータではなく、未来への期待を形にして示す手段といえるかもしれません。

ポイント6:社員や顧客の声を盛り込む
数字では伝えきれない「リアルさ」を補完するのが第三者の声です。
営業資料では、導入企業の声を事例として載せることで信頼性が高まります。あるソフトウェア企業は顧客インタビューを掲載し、導入前後の課題と解決のプロセスを紹介しました。これにより、読み手は自社の状況に置き換えて検討しやすくなりました。
採用資料では、社員の声が特に効果的です。ある企業は社員インタビュー動画を採用資料に組み込み、応募者から「働く姿がリアルにイメージできた」と好意的な反応を得ました。その結果、応募者数と質の両方が向上しました。
第三者の声は、人の感情を動かし、資料に温度感と説得力を与える重要な要素です。

ポイント7:フォント・配色に一貫性を持たせる
フォントや配色が統一されていない資料は雑然とした印象を与え、信頼性を損ないます。一貫性を持たせることは、視覚的な整理だけでなくブランドの一体感を表現する上でも重要です。
ある大手製造業は資料全体をブランドカラーで統一し、見た瞬間に企業イメージと結びつくように設計しました。また、別のスタートアップ企業は明るい色合いを採用資料で多用し、若い応募者に親しみやすさを感じさせました。
こうした統一感は細部に見える気配りであり、資料そのものの完成度を高め、企業の信頼につながります。

ポイント8:相手が行動に移しやすいCTAを設置する
会社紹介資料のゴールは、理解してもらうことではなく、行動につなげることです。
営業資料では「問い合わせフォーム」「無料デモの依頼」などを、採用資料では「エントリーはこちら」「説明会予約」などのCTA(Call To Action:行動喚起)を明確に設ける必要があります。
ある人材系企業は、採用資料の最後に応募フォームのQRコードを配置しました。その結果、説明会参加率が上がり、応募に直結するケースが増えました。行動を促す導線があるかどうかで、資料の成果は大きく変わります。

ポイント9:定期的に更新して鮮度を保つ
会社紹介資料は作って終わりではありません。最新の状態を維持することが信頼獲得につながります。
あるIT企業は営業資料を四半期ごとに見直し、新しい実績データを必ず更新しています。これにより顧客は「常に最新の成果を示してくれる企業」という印象を持ち、信頼度が増しました。
採用資料でも、年度ごとの制度変更や社内イベントを反映させている企業があります。古い情報を放置すると、応募者は「情報が古い=管理が甘い」と感じやすく、企業イメージを損ないます。
鮮度を維持することは、小さな手間で大きな成果を生むポイントです。

ポイント10:テンプレートを活用して効率化する
ゼロから資料を作るのは時間も労力もかかります。テンプレートを活用すれば効率的に質の高い資料を作成できます。
あるスタートアップは汎用テンプレートを活用しつつ、ブランドカラーとフォントを自社仕様に調整しました。その結果、工数を削減しながらも他社との差別化を実現しました。
また、ある中堅企業は複数部署で共通のテンプレートを用いることで、全社資料のデザイン統一を実現しました。効率化とブランド一貫性を同時に達成できたのです。
テンプレートはあくまで土台であり、自社らしさを加えることで、効率と独自性を両立できます。
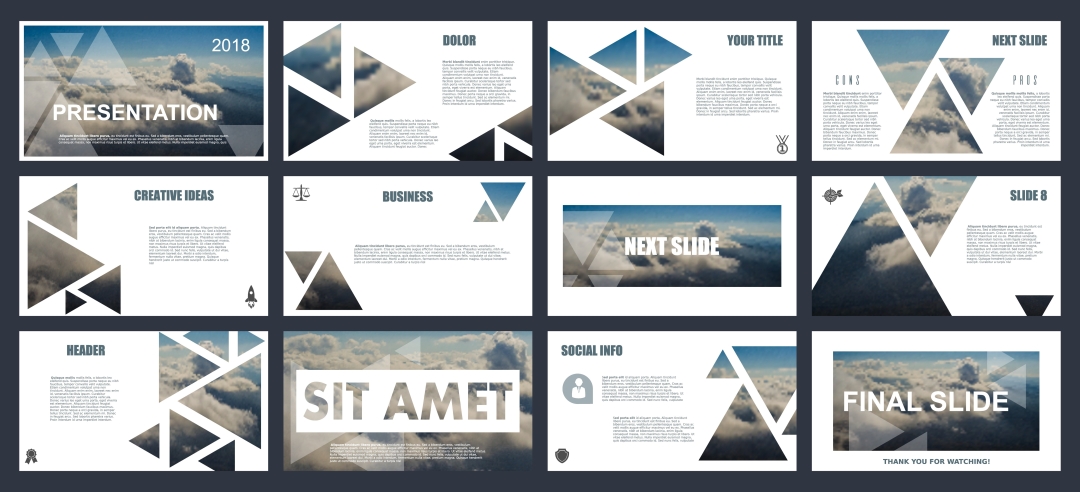
まとめ|営業・採用成果を高める会社紹介資料作成の秘訣
会社紹介資料は、営業や採用の成果を左右する重要なツールです。
ターゲットを明確にし、ストーリーを持たせ、1スライド1メッセージを徹底し、視覚的に理解できるデザインを行う。数字や声で信頼を補強し、デザインの一貫性を保ち、行動を促すCTA(Call To Action:行動喚起)を配置する。そして、定期的に更新し、テンプレートを活用して効率化する。
この10のポイントを実践すれば、会社紹介資料は単なる会社概要から、相手の行動を生み出す戦略資産へと進化します。改善を重ね続けることで、営業でも採用でも選ばれる企業になることができるはずです。ぜひ、皆さまの会社紹介資料でも実践してみてください!
ちなみに、「自分で資料を作るのは大変・・・」「プロの力を借りたい!」という方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください!1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。

目次