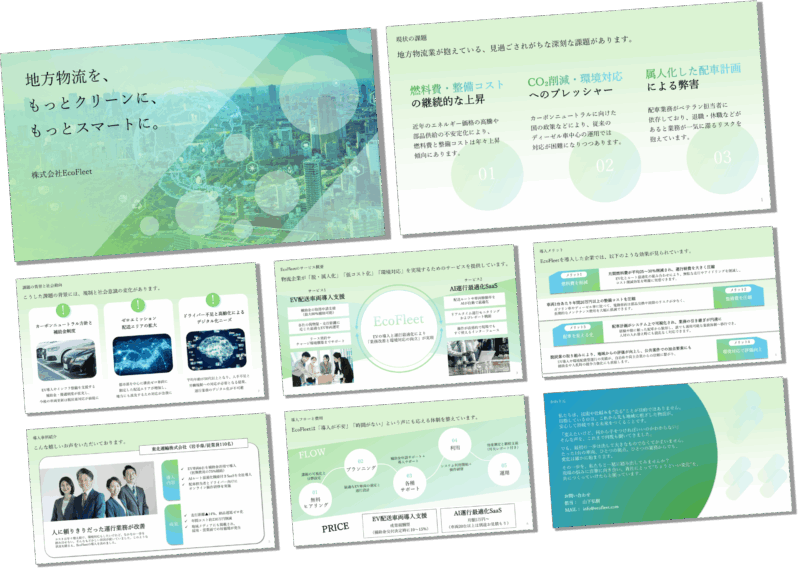営業活動において、営業資料は単なる説明スライドではなく、商談の流れと相手の意思決定をデザインするための設計図です。
面談の場でどれほど熱量のあるトークをしても、相手が社内に持ち帰って上司や関係部署へ説明する段階で、資料自体に論理性や再現性、客観的根拠がなければ説得力は急速に目減りします。とくにオンライン商談や非同期の検討が増えた今、営業担当者が同席しない「二次商談」は資料の品質で勝敗が決まります。だからこそ、読む人の疑問に先回りし、比較検討の基準を提示し、次のアクションに自然に進ませる勝ち筋のあるドキュメントを用意することが重要です。
本コラムでは、初心者でも成果につながる営業資料を作れるように、目的設定から構成、デザイン、事例提示、クロージング設計、運用改善までの要点を具体的に解説します。感覚論ではなく実務に直結する考え方と作り方に絞っているため、読み終えたその日から提案書の品質を底上げできるはずです。さあ、さっそく見ていきましょう!
なお、資料作成にお困りの方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください。1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます!

.png)
本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)
創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。
外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案や資料作成に関する豊富な経験を有する。
営業資料の役割|顧客を動かす「営業トークの相棒」にする
良い営業資料は、営業トークの抜けや偏りを補い、相手の頭の中で起きる理解の不足を補ってくれます。
顧客が本当に知りたいのは製品の自慢話ではなく、自社の課題と条件に照らして「なぜ今この提案が最適なのか」という合理的な理由です。そのため資料には、課題の解像度を上げる説明、意思決定に必要な数値、競合比較や代替案の扱い、導入プロセスとリスクの見通しなど、会話だと抜けがちな「後で問われるポイント」まで備えておく必要があります。
加えて、資料は社内稟議の場でも一人歩きします。担当者の熱量に依存せず、読み手が変わっても同じ結論にたどり着けるよう、見出しで結論を明示し、本文で根拠にリンクする構造を徹底しましょう。
営業資料とは、商談時間を短くし、意思決定の確度を高め、失注理由を減らすための「営業生産性のレバー」と言えるかもしれません。

コツ① 顧客が知りたいことから逆算して目的を決める
最初に決めるべきは「この資料を読んだ直後に相手に何をしてもらいたいか」という一点です。
見積依頼の獲得、デモ環境の発行、実証実験の合意、役員プレゼンへのエスカレーションなど、フェーズごとに最適なゴールは異なります。ゴールが決まれば、構成の取捨選択は一気に楽になり、語る順番や必要な証拠も自ずと定まります。初回接点なら課題の共感と適合性の提示を厚く、最終提案ならROI試算やリスク対策、導入計画の具体度を高める、といった具合です。
また読者像の設定も欠かせません。現場担当は運用負荷と使い勝手、決裁者は投資対効果とダウンサイドの小ささ、経営層は戦略的一貫性を重視します。
誰の疑問に答える資料なのかを一枚目から明確にし、見出しや言葉遣い、図解の粒度まで合わせることで、読み手は迷わず次の一歩を選べるようになります。

コツ② 顧客課題を掘り下げ、解決策に直結する構成を作る
提案は課題から始めるのが鉄則です。
「業務効率化」や「コスト削減」といった抽象語ではなく、現場で起きている具体的な問題を数値や事実で言語化し、なぜ今それが起きているのかという原因仮説まで踏み込みます。
たとえば問い合わせ対応の遅延が問題なら、ピークタイムの入電比率、一次解決率、ナレッジ検索時間などの指標で現状を可視化し、真因が人員不足なのかプロセス設計なのか、システムのUXなのかを切り分けます。
次に、解決策としての自社サービスを課題へ「線で結ぶ」ことが重要です。機能の列挙ではなく、どの摩擦にどの機能が効くのか、導入後に指標がどう変わるのかを、前後比較の図や簡潔な数式で示しましょう。
構成は「現状→課題→原因→解決策→期待効果→次の行動」。この一本道がブレない資料は、読み手の頭の中で自然とやる理由が積み上がります。

コツ③ 1スライド1メッセージで商談トークをシンプルにする
スライドは一枚につき主張を一つに絞り、見出しで結論を言い切ります。
「〇〇により一次解決率が30%改善」のように分かりやすいメッセージをタイトルに埋め込むと、流し読みでも要点が残ります。
本文はその根拠と補足だけに留め、冗長な説明は口頭で行いましょう。図は情報の交通整理役として使い、要素数を減らして視線の通り道を作ります。テキストの塊は短いセンテンスで段落を切り、強調は色ではなく位置と余白で示すと上品に収まります。
ありがちな失敗は、比較や導線、重要数値を一枚に詰め込みすぎてメッセージが曖昧になること。迷ったら「このページを閉じたときに、相手に残っていてほしい一文は何か」を自問し、その一文以外は削るか次ページに分ける判断基準を持つと、商談中のトークも驚くほど楽になります。

コツ④ データや事例で「納得感」と「説得力」を両立させる
意思決定を進めるのは感情と理性の両輪です。
理性には客観データ、感情にはストーリーが効きます。市場規模や成長率、費用対効果、工数削減、品質指標など、判断に必要な数字は出典と前提を添えて提示します。そのうえで、近しい業界・規模の導入事例を選び、導入前の躓き、意思決定の決め手、ローンチ後の定量成果を時系列で語ると、相手は自社に当てはめて想像しやすくなります。
競合比較は「フェア」が信頼の鍵です。弱みを隠さず、代替案が勝つ条件も明記しつつ、提案先における勝ち筋を具体的に示すことで、無理のない納得が生まれます。
グラフは結論を指し示すラベルを付け、軸や単位の不親切をなくし、凡例依存を減らします。「数字が語る物語」を仕立てられれば、説得は半ば終わります。

コツ⑤ 視覚的に理解しやすいレイアウトで記憶に残す
視覚設計の目的は「速く・正しく・忘れにくく」伝えることです。Z型やF型の視線誘導を意識し、重要情報は左上か中央に、補足は右下へ置きます。
余白は情報を減らすのではなく、情報の境界をはっきりさせるためのスペースです。要素間の距離を等間隔に保ち、整列の基準線を揃えるだけで、同じ内容でもプロの見栄えになります。
アイコンや写真は意味が生まれるところだけに限定し、装飾は我慢するのがコツ。文字サイズは投影環境で読めるかを基準に決め、オンラインなら画面共有の縮小を見越して一段階大きくします。
ページ遷移のリズムも成果に直結します。共感で入り、課題で腹落ちさせ、解決策で期待を作り、数値で確信に変え、最後に行動導線へ。読後に迷子を作らない視覚体験が、商談のスピードを上げます。

コツ⑥ ブランドイメージに沿った色とフォントで信頼感を醸成する
デザインの一貫性は信頼感に直結します。
色はベース・アクセント・注意の三系統に絞り、役割を固定します。たとえばベースはグレイ、アクセントは自社ブランドカラー、注意は赤系と決め、重要度に応じて濃淡で階層化します。
フォントは見出し・本文・注釈の三段でサイズとウェイトを定義し、行間も固定します。社名や製品ロゴの扱い、ヘッダー/フッターの情報位置、ページ番号の書式などをテンプレート化すれば、だれが作ってもブランド体験が揺れません。提案先の用語や表記ルールに寄り添う「軽いローカライズ」は効果大です。
相手の世界観に自分たちの提案をそっと置くことで、受け入れやすさが高まります。見た目は中身に勝てませんが、見た目の乱れは中身の信用を確実に削ります。整ったデザインは、その提案が任せて安心と思われるためのシグナルです。

コツ⑦ 提案内容は数字と比較で「選ばれる理由」を見せる
「当社A案」「競合B社」「現状維持」の3択で、費用、効果発現までの期間、運用工数、リスク、スケーラビリティなど評価軸を明示し、同一前提で横並びに示します。
ここで重要なのは「相手の社内で使われている評価軸」を採用すること。財務部門が気にする減価償却の年数、IT部門が気にするセキュリティ要件、現場が気にする移行時のダウンタイム。それらを比較表に組み込めば、資料は社内稟議の土台になります。
ROIは計算式を簡潔に開示し、感度分析で上下幅も見せると信頼が増します。弱点がある場合は回避策と運用ルールで補い、そのうえで「この条件なら当社が最適」という勝ち筋をはっきり示す。選ばれる理由は、こちらが作ってあげなければ相手の中に生まれません。

コツ⑧ 導入事例・成功事例で顧客心理を後押しする
人は未知より既知に安心します。
事例は「他社も成功している」という社会的証明を提供し、リスク知覚を下げます。最適なのは、業界・規模・課題構造が近い企業のストーリーです。導入前の苦労、検討時の迷い、決め手となった要因、オンボーディングの工夫、定量成果と副作用まで、良い面も課題も包み隠さず書くほど信頼は高まります。
数字は差分で語ると刺さります。たとえば応答率が70%→88%、処理時間が12分→5分など、ビフォーアフターを並べれば未来像が一瞬で伝わります。
最後に、事例企業の言葉や肩書を短く添えると、読み手は自分事化しやすくなります。
事例は華やかな飾りではありません。顧客が「自分たちでも再現できる」と信じるための、もっとも力のある材料です。

コツ⑨ クロージングを意識した「次の一歩」を設計する
営業資料の終盤は、相手の意思決定を歩きやすくするための区画と言えます。検討の段差をなくすには、行動の単位を小さく、負荷を明確にすることが効きます。
たとえば「30分のオンラインデモ」「2週間の無償トライアル(データ連携なし)」「試算に必要な情報一覧と提出フォーム」など、次の一歩を具体名で提示し、実施後に何が分かるのか、誰がどれだけ時間を使うのかまで書き添えます。
日程候補を3つ出す、責任者が押さえるべき承認ポイントを明記する、実施中の連絡チャネルを決める。こうした小さな設計が、商談の滞留を防ぎます。
クロージングは押し切ることではなく、相手が安心して前に進めるよう階段に手すりを付けることだと捉えましょう。

コツ⑩ 商談後のフィードバックで資料をアップデートする
勝てる資料は育てるものです。
商談ごとに「どのページで頷きが増えたか」「どこで質問が集中したか」「競合に負けた理由は何か」を記録し、月次で仮説と改定履歴を振り返ります。質問が多い箇所は先回りの説明を追加し、読み飛ばされるページは位置か主張を見直し、勝ち筋が変わったら比較軸ごと更新します。
営業、マーケ、カスタマーサクセス、プロダクトの横断でレビュー会を開き、最新の顧客インサイトと機能差分を反映させれば、資料は組織のナレッジになってくれます。
テンプレート化とバージョン管理を徹底し、成功事例や最新数値はモジュールとして差し替え可能にしておきましょう。継続的改善が、提案の再現性と成約率の両方を押し上げます。

まとめ|「売れる営業資料」を資産として育て続ける
営業資料は、個々のセンスに頼る属人的な産物ではなく、誰が作っても一定以上の成果が出る仕組みに変えられます。
目的と読者に合わせて設計し、課題から始めて解決策へ線を引き、数字と比較で選ばれる理由を作り、視覚設計で理解の段差をならし、事例で心理的安全性を高め、最後は次の一歩に手すりを付ける。さらに運用での気づきを反映し続ければ、資料は毎月強くなります。失注の悔しさも、更新の燃料に変わります。
今日からできる小さな改善を積み重ね、資料を組織の資産に成長させてください。それは商談のスピードと精度を同時に上げ、売上という最終成果に直結します。
ちなみに、「自分で資料を作るのは大変・・・」「プロの力を借りたい!」という方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください!1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。

目次