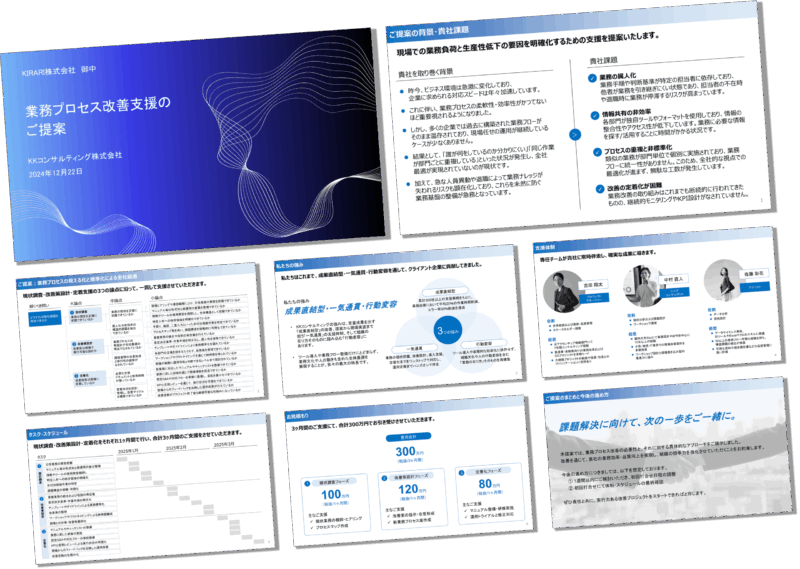提案書は、あなたのアイデアやサービスを相手に伝え、納得してもらい、行動してもらうための最重要ツールです。どれだけ優れた戦略やプランを考えても、デザインが整っていなければ、相手にとっては「読みにくい」「わかりにくい」「信頼できない」という印象を与えかねません。特に企業同士の取引やコンペでは、提案書は複数並べて比較されます。そのときに視覚的に洗練されているかどうかは、採用・不採用の分かれ目になることも少なくありません。
本記事をご覧になっている方の多くは、自分の資料が見づらいと感じているか、もっと相手に響く資料を作りたいと考えていると思います。そんな方たちのために、本記事では初心者でも実践できる10個のコツを紹介し、デザイン面から提案力を底上げする方法を徹底解説します!
なお、資料作成にお困りの方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください。1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます!

.png)
本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)
創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。
外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案や資料作成に関する豊富な経験を有する。
コツその①:提案書デザインの基本ルールを押さえる
まずは提案書デザインの基本ルールを理解することが大切です。
フォントは見出しと本文で統一感を持たせ、使う種類は最大2種類まで。見出しはゴシック体、本文は読みやすいサンセリフ系など、役割に合わせて使い分けましょう。配色は白や淡いグレーを背景に、黒や濃いグレーを基本文字色として用いると読みやすくなります。強調したい部分は1色だけアクセントカラーを加えると、全体が引き締まり、視線誘導がしやすくなります。
余白も重要なデザイン要素です。ページの端までびっしり文字や図が詰まっていると、読む前に疲れてしまいます。上下左右に十分なマージンを確保し、段落間に適度な間隔を入れることで、視覚的に整理された印象を与えられます。まずはこの「フォント統一」「配色ルール」「余白設計」を押さえるだけでも、提案書の見た目がぐっとプロフェッショナルになります。

コツその②:レイアウトは1ページ1メッセージに絞る
提案書デザインで最も多い失敗は、1ページに情報を詰め込みすぎることです。
読む人が一目で理解できるよう、1ページには1つのメッセージだけを載せるのが理想です。視線誘導を考え、重要な情報は左上に、補足情報は右下や下段に置くと自然な流れになります。
また、文章だけでなく箇条書きや図解を効果的に使いましょう。例えばメリットを説明するなら、3〜5個に絞った箇条書きにすると、読み手は短時間で内容を把握できます。ページ番号やセクション名を固定位置に置けば、資料全体の流れが把握しやすくなり、相手が途中で迷子になるのを防げます。

コツその③:配色で印象をコントロールする
提案書デザインでは色の選び方次第で相手に与える印象が変わります。
青系は信頼や誠実さ、緑系は安心感、オレンジや赤は情熱や行動喚起をイメージさせます。提案内容に合った色を選ぶことで、メッセージがより強く響きます。
配色は多くても3色以内に抑えると洗練された印象になります。文字色と背景色のコントラストが不足すると可読性が下がるため、黒×白、濃紺×淡いグレーといった高コントラストを意識しましょう。自信がない場合は、コーポレートカラーやブランドガイドラインに沿って作成するのがおすすめです。配色ツールを使えば初心者でもバランスの取れた組み合わせが見つかります。

コツその④:フォントと文字サイズの黄金比を守る
フォントと文字サイズは、提案書の可読性を大きく左右します。見出しは本文の1.5〜2倍程度のサイズに設定するとメリハリがつきます。例えば見出し24pt、本文14〜16pt程度が目安です。行間は文字サイズの1.3〜1.5倍確保することで、窮屈さを解消できます。
フォント選びも重要です。明朝体はフォーマルさや落ち着きを表現し、ゴシック体はモダンさや親しみやすさを与えます。提案内容が公共性の高いものか、スタートアップ向けかによって使い分けると良いでしょう。色は黒に近い濃いグレーを選ぶと、長時間読んでも疲れにくいです。

コツその⑤:図解・アイコン・写真で視覚的に訴える
提案書では、文字だけよりも視覚情報を多用した方が理解が早くなります。
売上比較や費用対効果の説明では、表ではなく棒グラフや円グラフを使うとひと目で差が分かります。プロセスや流れはフローチャートで表現すると、順序関係が明確になります。
アイコンや写真は、高解像度かつ統一感のあるものを選びましょう。フリー素材を使う際は著作権を確認し、色味やテイストが揃っているかも意識すると全体が整います。写真の余白を活かして、文字とバランスよく配置することで見栄えが大幅に向上します。

コツその⑥:見出しとナンバリングでストーリーを作る
提案書は単なる情報の羅列ではなく、ストーリーとして相手に体験してもらう資料です。見出しは短く端的にし、ページをめくるたびに次の展開が気になる構成にしましょう。
ナンバリングをつけると論理の流れが明確になり、読み手はどこにいるかを常に把握できます。例えば、「1. 課題」「2. 解決策」「3. 導入メリット」「4. コスト」「5. 次のステップ」という流れにすると、自然に納得感が高まります。

コツその⑦:テンプレートを活用して効率化する
ゼロから作るのは時間がかかるため、テンプレートを活用すると効率的です。PowerPointやCanva、Googleスライドには無料テンプレートが多数あり、ベースとして使えば短時間で整ったデザインが作れます。
ただしそのまま使うと他社と似通った提案書になるので、自社ロゴやコーポレートカラーを取り入れ、見出しやアイコンを調整しましょう。テンプレートを整備しておくと、次回以降はスライドを差し替えるだけで新しい提案書が作れるため、長期的に大きな時短になります。

コツその⑧:仕上げにチェックリストで整える
提案書が完成したら、チェックリストで細部まで確認します。誤字脱字がないか、フォントや文字サイズが統一されているか、配色に違和感がないか、スライド番号や見出しの位置が揃っているかを必ずチェックしましょう。リンクやQRコードが正しく機能するか、添付資料が抜けていないかも確認が必要です。
この工程を省略すると、せっかくの提案書が些細なミスで信頼を失う可能性があります。毎回同じチェックリストを使えば、品質を一定以上に保つことができます。

コツその⑨:良い提案書と悪い提案書の事例を比較する
デザインの良し悪しを理解するには、具体的な事例を比較するのが一番です。悪い提案書は情報過多、フォントや色がバラバラ、ページごとにデザインが異なるなど、読む人を混乱させる要素が目立ちます。
一方、良い提案書は余白が適度にあり、見出しが明確、視覚的にわかりやすいグラフやアイコンが使われています。実際にビフォーアフターを並べると、同じ内容でもデザインを整えるだけで相手の理解度や納得感が格段に向上することがわかります。

コツその⑩:第三者レビューで最終確認を行う
自分では完璧に仕上げたつもりでも、他人の目で見ると改善点が見つかることは多いです。同僚や上司、できれば顧客目線に近い人に提案書を見てもらいましょう。
「どこで読みづらさを感じたか」「どのページで納得感が薄れたか」をヒアリングすると、次回以降の改善に直結します。第三者レビューを取り入れるだけで、提案書の質は確実にワンランク上がります。

まとめ|次の提案書から実践できるポイント
提案書デザインはちょっとした工夫で大きく変わります。まずは基本ルールを押さえ、配色やレイアウトを整えて統一感を出すことから始めましょう。次に図解やアイコンを加え、視覚的にわかりやすい資料に仕上げます。そして最後に第三者レビューで客観的な視点を取り入れると、完成度が飛躍的に高まります。
デザインはセンスではなく技術です。誰でも学べば上達できるスキルなので、今日からぜひ実践してみてください。
ちなみに、「自分で資料を作るのは大変・・・」「プロの力を借りたい!」という方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください!1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。

目次