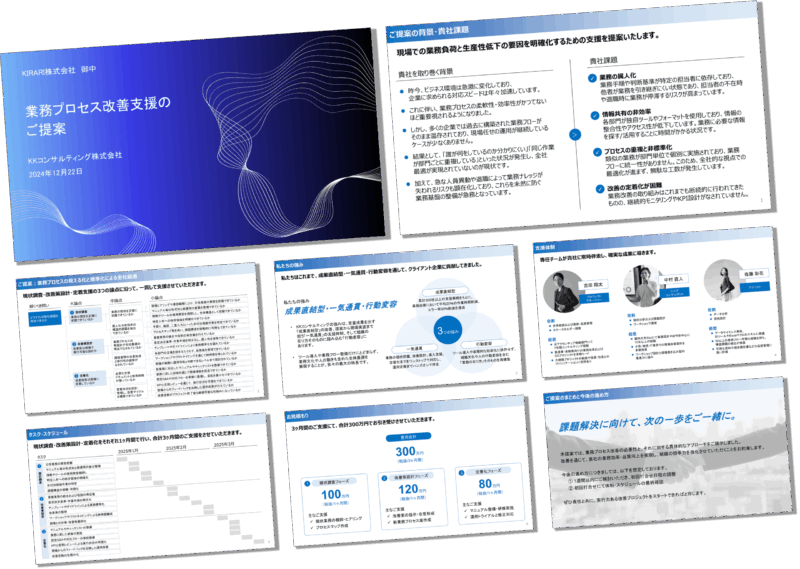提案書は、あなたのアイデアやサービスを相手に理解してもらい、採用してもらうための大切なプレゼンテーションツールです。しかし、現実には「なかなか通らない」「最後のひと押しで負けた」という経験を持つ方も多いのではないでしょうか。提案書が通らない理由は、アイデアの良し悪しだけではありません。多くの場合、伝え方に問題があります。
提案書は、ただ情報を並べれば良いというものではありません。相手が「読む気になる」「理解できる」「納得できる」状態にする必要があります。ビジネスの現場では、担当者や決裁者が限られた時間で複数の提案書を比較します。その中で目に留まるためには、内容の正確さと同じくらい、構成やデザイン、説得力が重要です。
さらに、提案書が通らない典型的な原因としては、次のようなものがあります。目的やターゲットが曖昧なまま作成されている、情報が整理されていない、論理の流れが飛んでいる、読み手が次に何をすれば良いかわからない。このような状態では、どれだけ良い提案でも相手に届かず、結果的に不採用になる可能性が高まります。
この記事では、提案書が通らない理由を整理した上で、やりがちな失敗とNG例を紹介し、正しい作り方の型とコツを解説します。最後には、作成後に必ず行いたいチェックポイントと、失敗しないための心構えをまとめました。この記事を読むことで、次に作る提案書の質を大幅に高め、採用率を上げることができます。
なお、資料作成にお困りの方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください。1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます!

.png)
本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)
創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。
外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案や資料作成に関する豊富な経験を有する。
提案書作成でやりがちな失敗とNG例
多くの人が提案書作成でやってしまう典型的な失敗を整理しておきましょう。これらを避けるだけでも、提案書の完成度は格段に上がります。
まず一番多いのが「目的不明確」。提案書を書き始める前に「誰に、何を、どうしてほしいか」を定義していないケースです。結果として、相手が読んでも結論がわからず、「で、何をすればいいの?」と感じる資料になってしまいます。
次に多いのが「情報詰め込みすぎ」。良かれと思って大量の情報を盛り込み、ページが文字だらけになるケースです。読む側は情報量に圧倒され、必要なポイントを拾えません。特に数字やデータをただ羅列してしまうと、分析の意図が伝わらず「だから何?」で終わってしまいます。
「論理の飛躍」もよくある問題です。現状説明からいきなり提案に飛び、なぜその解決策が必要なのかが抜けていると、読み手は納得できません。ストーリーの流れが分断されている提案書は、どんなにデザインがきれいでも説得力を欠きます。
「デザインが雑」というのも見逃せないNGです。フォントやサイズがバラバラ、色使いが統一されていない、余白が詰まりすぎていると、読み手はストレスを感じます。内容以前に「ちゃんと作られていない」という印象を与えてしまいます。
最後に「次のアクションが書かれていない」という致命的なミス。提案書は読むためではなく、行動を起こしてもらうための資料です。「承認してください」「検討会を設定してください」といった明確な行動喚起が抜けていると、せっかくの提案も宙に浮いてしまいます。

正しい提案書の作り方(基本の型)
では、失敗を避けるためにどう作れば良いか。提案書には基本となる「型」があります。これを意識して作成するだけで、資料全体の説得力が格段に高まります。
まず「目的とターゲット」を明確にすること。提案書を読むのが誰なのか、何を決める立場の人なのかをはっきりさせます。経営層ならROIやリスクが重要、現場担当者なら具体的な運用手順や負荷が気になります。
次に「構成を決める」。基本的な構成は以下の通りです。
・表紙(タイトル、日付、作成者)
・目的・背景(提案の意義)
・現状と課題(データと事実)
・解決策(提案内容)
・導入効果(メリット、数値効果)
・実施計画(スケジュール、体制)
・コスト(費用の見積もり)
・まとめと行動喚起
この流れは、現状→課題→解決策→効果→実施→コスト→結論という「ストーリー」を自然に作ります。相手は段階的に納得していくので、結論が受け入れやすくなります。
文章は短く簡潔に。1ページ1メッセージを徹底し、視覚的にわかる図やグラフを活用します。データはただ並べるのではなく「何を示したいのか」を明確に書き添えることで説得力が高まります。
最後に、提案書には必ず「次のステップ」を書きます。「承認をお願いします」「次回会議でご検討ください」「見積もり承認後、〇月から実施可能です」といった具体的な行動喚起があることで、相手は次に何をすればいいか迷いません。

読まれる提案書にするコツ
提案書は内容が正しくても、読まれなければ意味がありません。読まれる提案書にするための工夫を紹介します。
まず「視覚的なわかりやすさ」。余白をしっかり取り、文字は詰め込みすぎない。フォントや色を統一し、見出しは大きく太字にしてメリハリをつけます。重要な数字や結論は強調表示して、視線が自然に集まるようにします。
次に「ストーリー性」。提案書は情報ではなく物語です。「現状→課題→解決策→効果→行動」という流れを崩さず、読み進めるうちに自然と「この提案はやるべきだ」と思わせる構成にします。ページをめくるたびに次が気になるような流れを意識しましょう。
さらに「データと事例の使い方」。データは説得力の源泉ですが、数字の羅列は逆効果です。グラフ化し、ビフォーアフターを見せることで、変化のイメージが湧きやすくなります。事例紹介を入れると、提案内容が現実的で再現可能であることが伝わります。
そして「相手目線」。提案書は自分の言いたいことを書く場ではなく、相手が知りたいことを書く場です。「相手がどんな懸念を持つか」「何を基準に判断するか」を想像し、それに答える形で情報を配置します。
こうしたコツを理解するだけでも、提案書の品質が随分と向上します。ぜひ実践してみてください!

作成後に必ず確認すべきポイント
提案書が完成したら、必ずチェックを行います。ここで手を抜くと、小さなミスで信頼を損なう可能性があります。チェックリストとして、提案書の作成前後に確認するようにしましょう。
まず「誤字脱字」。基本中の基本ですが、意外と残っています。次に「数字や単位の整合性」。金額、パーセント、日付などがページごとに食い違っていないか確認します。
「構成の一貫性」も重要です。見出しのフォント、サイズ、色は揃っているか。箇条書きの記号は統一されているか。ページ番号は振られているか。これらが揃っていないと、全体の印象が雑になります。
さらに「論理の流れ」。冒頭の課題設定から結論まで、筋道が飛んでいないか確認しましょう。第三者レビューを取り入れると、論理の飛躍や説明不足に気づきやすくなります。
最後に「行動喚起」が明確かどうかを再チェック。「誰が」「いつまでに」「何をするのか」が明記されているかを確認し、次のステップがスムーズになるように整えます。

まとめ|失敗しない提案書作成の心構え
提案書は「情報整理」「説得ストーリー」「デザイン」「行動喚起」の4つが揃って初めて完成します。目的やターゲットを明確にし、構成を整え、説得力のある根拠とわかりやすいデザインで仕上げる。最後にしっかりとチェックを行い、次のアクションを明確にする。これが失敗しない提案書作成の基本です。
提案書作りは一度で完璧になるものではありません。作るたびにレビューを受け、改善を積み重ねることで、どんどん質が高まります。この記事で紹介したポイントを次の提案書からぜひ実践し、あなたの提案が通る確率を高めていきましょう。
ちなみに、「自分で資料を作るのは大変・・・」「プロの力を借りたい!」という方は、「Business Jungle資料作成」をご利用ください!1枚3,000円から、あっと驚く資料作成のお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談くださいませ。

目次