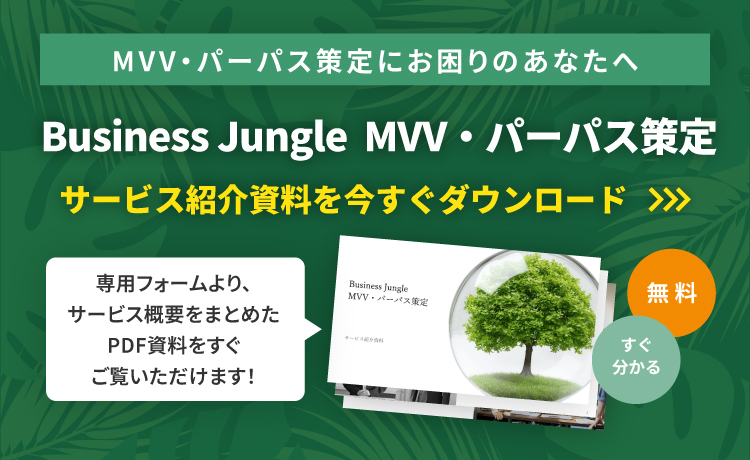最近、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスという言葉を耳にする機会が増えたと感じている方は多いのではないでしょうか。
この記事では、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスといった言葉が注目されている背景や定義、それぞれの違いまで細かくご説明させていただきます。さあ、それでは中身を見ていきましょう!
なお、わたしたち「Business Jungle MVV・パーパス策定」と一緒にMVV・パーパスを策定したい方は、いつでもご連絡ください。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、全力でサポートさせていただきます!

.png)
本記事の監修 松浦英宗(まつうらえいしゅう)
創業・事業成長に必要なサービスをオールインワンで提供するBusiness Jungleの代表。
外資系戦略コンサルティング会社(アーサー・ディ・リトル・ジャパン)などにおいて、事業戦略立案やMVV・パーパスの策定・浸透に関する豊富な経験を有する。
はじめに:MVVやパーパスを一言で言うと
そもそもMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスとは何かご存じでしょうか。
一言でいえば「企業が成長していくための羅針盤」であり、それぞれミッション(果たすべき使命)・ビジョン(将来の理想的な姿)・バリュー(大切にしたい価値観)・パーパス(存在意義)という意味があります。
これらが組織における共通言語となり、企業は継続的な成長を実現することができるようになります。反対に、こうした共通言語がなければ、さまざまな思想を持った人間が、各々好きな方向を目指して活動してしまい、結果として組織機能が著しく低下してしまいます。
では、実際にMVVとパーパスの定義や関係性について掘り下げていきましょう。

ミッション(果たすべき使命)とは
ミッションはMVVのうち上段の概念に該当し、日本語では「果たすべき使命」と訳されます。
「私たちが果たすべきことは何か?」という問いに対する答えとも言うことができます。
ミッションが明確であれば、自社で意思決定・行動する際の判断基準がブレなくなります。例えば、とある投資案件が短期的に収益は見込まれないような場合でも、自社のミッションに整合する場合は投資が実行され、その反対にミッションに整合しない案件は投資が実行されないといった具合です。
このようにミッションが策定・浸透していることで、目の前の業務が単なる作業ではなく、社会や顧客に対してどのような意味を持つかが見えてきます。社員の意識統一や組織文化の形成にもつながり、スタートアップや成長企業にとっては、短期的な混乱を乗り越える「原点」として機能します。
具体的な例を挙げると、パタゴニアのミッションである「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む」が有名です。これは単なるアパレル企業としての役割ではなく、環境保護を中核とする企業としての役割を示しており、実際に同社は株式の98%を環境NPOのHoldfast Collectiveに、残りの2%をPatagonia Purpose Trustに譲渡するなど、ミッションを行動で体現しています。
このようにミッションは、自分たちが果たすべき使命を簡潔にまとめた宣言であり、自分たちのあらゆる意思決定・行動の原点として機能します。

ビジョン(将来の理想的な姿)とは
ビジョンはMVVのうち中段の概念に該当し、日本語では「将来の理想的な姿」と訳されます。
「ミッションの実現に向けて、私たちはどうありたいか?」という問いに対する答えとも言うことができます。
ミッションは自分たちのあらゆる判断の拠り所でしたが、これだけでは抽象的すぎて何を目指すべきか分かりません。しかし、ミッションを踏まえてビジョンを定義してあげると、自分たちの意思決定・行動の一つ一つがどこに向かうための取り組みであるかが明確になります。
例を挙げると、パナソニックはミッションを「Life tech & ideas 人・社会・地球を健やかにする。」として定義し、ビジョンを「人を想う技術と創造力でくらしを支えるベストパートナー」として定義しています。
ミッションだけでは広がりはあるものの抽象的でしたが、ビジョンがあることでパナソニックがどのように人・社会・地球を健やかにするのかが明確になったことが分かると思います。

バリュー(大切にしたい価値観)とは
バリューはMVVのうち下段の概念に該当し、日本語では「大切にしたい価値観」と訳されます。
「私たちがどうしても譲れない考え方は何か?」という問いに対する答えとも言うことができます。
組織が小さいうちは、バリューがなくとも組織として機能させることができます。しかしながら、組織が大きくなるにつれて異なる価値観を持つ人材が増え、その結果意見の衝突やそれに伴う意思決定の遅延などが発生し、各人材にとって「なんだか過ごしにくい組織」ができあがってしまいます。
このような事態を避け、ミッションやビジョンの実現に向けて最大効率で組織を機能させるための指針がバリューです。これは決して多様性を排除しようという概念ではなく、多様性を尊重しながらも誰もが過ごしやすい組織にするために最低限守るべきルールです。
例えば、デジタル庁のバリューは「一人ひとりのために」「常に目的を問い」「あらゆる立場を超えて」「成果への挑戦を続けます」であり、国家という目線であらゆる人を守ろうとする意思が感じられます。
また、メルカリのバリューは「Go Bold 大胆にやろう」「All for One 全ては成功のために」「Be a Pro プロフェッショナルであれ」「Move Fast はやく動く」であり、急スピードで成長してきた歴史や能動性が感じられます。
このように、バリューは自分たちがどうしても譲れない想いを表現し、仕事を進めるうえでのルールや、採用時に人を引き付ける/共感を得るための指針として活用していくことになります。

パーパス(存在意義)とは?ミッションとの違いは
パーパスは日本語では「存在意義」と訳され、MVVとは異なる概念として整理されることが多いです。
「私たちは何のために存在しているのか?」という問いに対する答えとも言うことができます。
近年、サステナビリティや多様性、社会課題への対応が求められるなかで、企業が利益だけを追うのではなく、社会的意義を伴った存在であることが求められるようになっています。そんな時代において、パーパスは企業が社会・顧客・社員との信頼を築くための軸となります。
有名な事例を挙げると、Sonyは「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」というパーパスを掲げています。これは2019年に同社がMVVを見直す過程で策定したものであり、現在はパーパスとバリューの2本柱に基づいて事業を推進しており、従業員からも大きな共感を得ています。

ここで勘のよい方は「あれ、ミッション(果たすべき使命)とパーパス(存在意義)との違いって何だ?」と思ったかもしれません。教科書的な違いを説明させていただくと、ミッションは「私たちは〇〇しなくてはならない」というかたちで外的動機をもとに定められるものであり、パーパスは「私たちは〇〇するためにある」というかたちで内的動機をもとに定められるものです。
これだけを聞くとミッションは悪で、パーパスは善であるように聞こえてしまいますが、そんなことはまったくありません。
そもそもミッションを存在意義として定義し、内的動機を表現している企業は数え切れないほどあります。ミッションとパーパスを両方掲げている企業もあれば、いずれかだけ掲げている企業もあります。さらに言えば、MVVの一部のみしか設定していない企業や、MVVという表現を使用していない企業も山ほどあります。
要するに重要なことは、企業にとって拠り所となる羅針盤を正しく備え、社内に浸透させるということでしかなく、MVVやパーパスに関する唯一無二の正しい定義・活用方法(答え)はありません。
ミッションが外的動機をもとにした消極的な内容になっているのであれば、それを内的動機が起点となるようにアップデートしてもよいです。あるいは、ミッションの上位概念としてパーパスを設定してもよいです。自社の状況に応じて、パーパスという考え方の取り扱いを決めることが大切です。
あなたの企業にとっての最適は何でしょうか。
現状のMVVを刷新すること、新しくパーパスを策定すること、既存のMVV・パーパスの浸透に努めること。さまざまな選択肢がありますが、大事なことは企業にとって拠り所となる羅針盤を正しく備え、社内に浸透させるということです。これを忘れずに、取るべきアクションを検討・実践してください。

まとめ:MVV・パーパスは企業の羅針盤
現代の企業において、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスは、単なる理念やスローガンではなく、企業が迷わず前進するための「羅針盤」であり、あらゆる判断や行動の根幹を支える存在です。
ミッションは「果たすべき使命」、ビジョンは「将来の理想的な姿」、バリューは「大切にしたい価値観」、そしてパーパスは「存在意義」という根源的な問いに対する答えです。これらを言語化し、組織の内外に浸透させることができれば、企業は環境の変化に動じることなく、ぶれない軸を持って行動し続けることができます。
そして重要なのは、教科書的な定義にとらわれることではなく、自社にとって本当に大切な考え方を整理することであり、MVVやパーパスという言葉自体に大きくこだわる必要はありません。形式にこだわるのではなく、自分たちにとってのリアルで血の通った言葉として、MVVやパーパスを構築・運用していくことこそが、企業の持続的成長と信頼構築のカギとなります。
MVVやパーパスは、組織がバラバラになりそうなとき、判断に迷うとき、成長の方向性に悩むときに立ち返る原点であり、羅針盤です。これを言語化し、共有し、日々の意思決定に根付かせていくことで、企業は真に力強く、しなやかに進化し続けることができます。ぜひこの機会に、自社のMVV・パーパスの策定や見直しに取り組んでみてください。
もし、MVVやパーパスの言語化や社内展開にお悩みであれば、私たち「Business Jungle MVV・パーパス策定」がお手伝いできるかもしれません。外資戦略コンサルやデザイナー出身者を含む多様な専門チームが、あなたの会社らしいMVV・パーパスを共にかたちにします。

目次